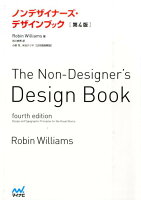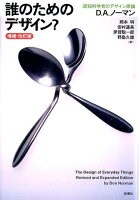概要

開発現場で頻発する「イメージと違う」という手戻りや、ユーザーの「使いにくい」という声。その根源は、曖昧な画面設計にあります。本レポートでは、システム開発の実務家から絶大な信頼を得る『設計シリーズ:3 画面設計書』をバイブルと位置づけ、論理的で網羅的な画面設計書の作成技術を深掘りします。
本書が教える思考プロセス、状態変化の網羅性、実践的なフォーマットの価値を解説。さらに、UIデザイン原則、人間中心設計、情報アーキテクチャ、UXライティングの名著も紹介し、あなたの設計スキルを飛躍的に高める知識体系を提示します。感覚的なお絵描きから脱却し、開発の羅針盤となる本物の設計スキルを身につけましょう。
-

【設計シリーズ】システム開発でよく使う設計書 TOP20
システム開発の現場で必須となる設計書をTOP20ランキングでご紹介。開発の起点となる要件定義書から、品質保証のためのテスト仕様書、円滑な運用を支えるマニュアルまで。各ドキュメントの役割と重要性を簡潔に解説し、プロジェクト全体の流れを可視化します。エンジニアやPM必携の知識です。
続きを見る
目次
はじめに:サイレントな悲鳴が聞こえますか?
「このボタン、何のためにあるの?」
「入力項目が多すぎて、どこから手をつけていいか分からない…」
「結局、この画面で何がしたかったんだっけ?」
ユーザーがあなたの作ったシステムやアプリの画面を前に、静かに、しかし確実に感じているフラストレーション。そのサイレントな悲鳴は、サービスの離脱率、顧客満足度の低下、そして最終的にはビジネスの機会損失という形で、あなたの元に跳ね返ってきます。
開発現場では、こんな言葉が飛び交っていないでしょうか。
- エンジニア: 「仕様が曖昧すぎて作れない。後から『イメージと違う』と言われても困る。」
- ディレクター: 「デザイナーに何度も修正をお願いして申し訳ない。でも、何が正解か分からないんだ。」
- 経営者: 「開発に時間もコストもかかったのに、なぜか使いにくい。一体、どこで間違えたんだろう?」
これらの問題の根源は、驚くほど共通しています。それは、プロジェクトの初期段階における「画面設計の欠如」あるいは「質の低い画面設計」に他なりません。
なんとなくのワイヤーフレーム、雰囲気だけのデザインカンプ、口頭での曖昧な指示。これらは一見、スピード感があるように見えて、実はプロジェクトの進行を阻害し、手戻りの山を築き、関係者の疲弊を招く「時限爆弾」を仕込んでいるのと同じです。
もし、あなたが今、
- 自分が作る画面の「分かりやすさ」に自信が持てない
- 開発者や関係者とのコミュニケーションで、画面イメージの齟齬に苦しんでいる
- 手戻りや修正依頼の多さに、心身ともにすり減っている
- UI/UXデザインの重要性は理解しているが、何から学べばいいか分からない
- 感覚ではなく、論理的に「良い画面」を設計するスキルを身につけたい
と感じているのなら、この先を読み進めてください。
本稿は、単なる書籍紹介ではありません。あなたのキャリアを、そしてあなたのチームを、混沌とした開発現場から救い出し、ユーザーに心から「使いやすい」と評価されるサービスを生み出すための「設計思想」と、その具体的な「武器」を手に入れるためのロードマップです。
その中心に据えるのが、知る人ぞ知る、しかし現場の実務家から絶大な信頼を得ている名著『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』です。この記事を読み終える頃には、なぜこの一冊があなたの仕事の「バイブル」となり得るのか、そして、あなたの作る画面が劇的に変わる未来を、はっきりと確信できるはずです。
第1部:画面設計書は「お絵描き」ではない — 開発の成否を分ける羅針盤
多くの人が誤解していますが、画面設計書は単なる「画面の絵(レイアウト)」ではありません。それは、「ユーザーとの対話」を設計し、「開発者との共通言語」を確立し、「ビジネス目標を達成するための戦略」を可視化した、プロジェクトの羅針盤です。
なぜ、優れた画面設計書が必要不可欠なのか?
優れた画面設計書は、プロジェクトに計り知れないメリットをもたらします。
- 手戻りの劇的な削減: プロジェクト失敗の最大の原因である「手戻り」。仕様の認識齟齬を初期段階で徹底的に潰すことで、開発終盤での「やっぱりこうじゃなかった」という致命的な修正を防ぎます。これは、コストと時間の浪費を直接的に防ぐ、最も効果的な投資です。
- 開発スピードの向上: エンジニアは「この画面は何をするべきか」「このボタンを押したらどうなるのか」といった疑問に悩むことなく、実装に集中できます。明確な設計書は、エンジニアの迷いをなくし、コーディングの速度を飛躍的に高めます。
- コミュニケーションコストの削減: 「あれ、どうでしたっけ?」「この部分、どうします?」といった不毛な確認作業がなくなります。設計書が「唯一の正義」として機能し、関係者全員が同じゴールを見て進むことができます。
- 品質の担保と向上: 画面上の全ての要素(ボタン、ラベル、入力フォーム、メッセージなど)に設計者の意図が込められるため、一貫性のある、質の高いユーザーインターフェースが実現します。属人性を排し、誰が作っても一定の品質を保てるようになります。
- ユーザー満足度の向上: これが最も重要です。論理的に設計された画面は、ユーザーを迷わせません。直感的で、ストレスなく目的を達成できる体験は、ユーザーに「このサービスは信頼できる」「また使いたい」というポジティブな感情を抱かせます。
逆に、質の低い画面設計書、あるいはそれ自体が存在しないプロジェクトは、嵐の海を羅針盤なしで航海するようなものです。いつか必ず座礁します。
あなたの現場は大丈夫? 画面設計のアンチパターン
あなたの周りで、こんな光景は見られませんか?
graph TD
subgraph "アンチパターンが生む負のスパイラル"
A["曖昧な仕様・口頭指示"] --> B{"<br>関係者の解釈が分裂"};
B -- "エンジニアの推測" --> C["手探りでの実装<br>(仕様確認の往復)"];
B -- "デザイナーの忖度" --> D["意図と乖離したデザイン<br>(無限の修正依頼)"];
C --> E["<br><b>致命的な手戻りの発生</b>"];
D --> E;
E --> F["スケジュール遅延<br>コスト超過<br>品質低下"];
F --> G["チームの疲弊<br>モチベーション低下<br>信頼関係の崩壊"];
G --> H["さらに曖昧な指示が横行<br>(悪しき文化の定着)"];
H --> A;
end
style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
style E fill:#ff9999,stroke:#333,stroke-width:4px
style G fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px- 口頭伝承型: 「ここはこんな感じで、シュッとスライドして情報が出てくるようにして」といった曖昧な指示が飛び交う。結果、人によって解釈がバラバラになる。
- 雰囲気ワイヤーフレーム型: 要素の配置だけが描かれた、魂のないワイヤーフレーム。エラー時はどうなる?データが0件の時は?ローディング中は?といった、肝心な状態変化が全く考慮されていない。
- デザイナー丸投げ型: 「いい感じにしといて」と、デザイナーに全ての判断を委ねてしまう。ビジネス要件やシステム制約を無視したデザインが生まれ、後から実装不可能だと判明する。
- パワポ方眼紙型: PowerPointやExcelで作成され、レイアウトの意図やコンポーネントの仕様が全く記述されていない「見た目だけ」の資料。メンテナンス性が最悪で、すぐに陳腐化する。
これらのアンチパターンは、一時的には仕事が進んでいるように見えますが、確実にプロジェクトの未来に負債を溜め込んでいます。この負のスパイラルから抜け出すためには、体系的で、論理的で、誰が見ても理解できる「本物の画面設計書」を作成する技術が不可欠なのです。
第2部:なぜ『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』があなたの「バイブル」になるのか
数多あるUI/UX関連書籍の中で、なぜ私たちはこれほどまでに『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』(著:スリーネクスト)を強く推奨するのでしょうか。それは、この書籍が「デザイナー向けのおしゃれなデザイン論」でも、「エンジニア向けの小手先のテクニック集」でもない、システム開発の現場で即座に機能する、極めて実践的な「設計」の方法論を提示しているからです。
この本は「誰」のための本か?
本書は、特定の職種のためだけのものではありません。
- システムエンジニア(SE)・プログラマー: 感覚ではなく、論理的にUIを構築するスキルが身につきます。デザイナーやディレクターとのコミュニケーションが円滑になり、実装の手戻りが激減します。
- Webディレクター・プロジェクトマネージャー: 関係者との合意形成をスムーズに進めるための「共通言語」を手に入れられます。プロジェクトの品質とスケジュールを管理する強力な武器となります。
- UI/UXデザイナー: 自身のデザインの意図を、誰にでも分かりやすく説明できるようになります。エンジニアに「なぜこのデザインなのか」を明確に伝え、実装精度を高めることができます。
- これからIT業界を目指す学生・若手: 現場で求められる「本物の設計スキル」の基礎を学ぶことができます。他の候補者と圧倒的な差をつける、確かな知識基盤を築けます。
つまり、「ユーザーに届く画面」に関わるすべての人にとって、必読の一冊と言えます。
他のUI/UX本と一線を画す、本書の圧倒的な「強み」
本書の比類なき価値は、その徹底した「体系化」と「網羅性」にあります。UIデザインを、センスや感性の世界から、技術と科学の世界へと引きずり下ろしてくれます。
mindmap
root("『設計シリーズ:3』の圧倒的な強み")
"強み1: 思考のプロセスから学べる<br><b>「なぜ、そう設計するのか」</b>"
("画面構成要素")
("画面操作要素")
("画面入出力要素")
("→ 認知心理学に基づいた論理的解説")
"強み2: 悪魔は細部に宿る<br><b>「状態変化」の完全な網羅</b>"
("初期表示 (ゼロステート)")
("入力中 (フィードバック)")
("処理中 (ローディング)")
("処理後 (成功/失敗)")
("境界系 (データ最大/最小)")
("異常系 (エラー全般)")
("→ 手戻り原因の根本を絶つ")
"強み3: そのまま使える<br><b>「ドキュメントフォーマット」</b>"
("画面レイアウト図")
("画面項目定義書")
("画面遷移図との連携")
("CRUD図との連携")
("→ チームの共通言語を即導入")- 強み1:思考のプロセスから学べる「なぜ、そう設計するのか」 本書は単なるレイアウトパターン集ではありません。「画面」を構成する要素を「画面構成要素」「画面操作要素」「画面入出力要素」という3つのカテゴリに分類し、それぞれが持つ役割と、ユーザーに与える心理的影響、そして設計上の注意点を徹底的に解説します。 例えば、「ボタン」一つとっても、「プライマリボタンとセカンダリボタンの使い分け」「ラベルの文言」「配置場所の原則」など、なぜそのデザインが最適なのかを、認知心理学の観点も交えながら論理的に説明してくれます。これにより、あなたは「なんとなく」のデザインから脱却し、全ての配置に明確な意図を持たせることができるようになります。
- 強み2:悪魔は細部に宿る。「状態変化」の完全な網羅 優れたUIは、正常系だけでなく、異常系や境界系の振る舞いが丁寧に設計されています。本書の真骨頂は、この「状態変化」の設計にあります。
- 初期表示: データがまだ何もない状態の画面(ゼロステート)をどう見せるか?
- 入力中: 入力エラーのフィードバックをどのタイミングで、どのように表示するか?
- 処理中: ローディングやプログレス表示をどう見せ、ユーザーの不安を解消するか?
- 処理後: 成功メッセージ、失敗メッセージをどう伝え、次のアクションに繋げるか? これらの細かな状態変化を事前に定義しておくことが、手戻りを防ぎ、ユーザー体験を劇的に向上させます。本書は、あなたが考慮すべき状態変化のチェックリストとして、完璧に機能します。
- 強み3:そのまま使える「ドキュメントフォーマット」 知識を学んでも、それをどうドキュメントに落とし込めばいいか分からなければ意味がありません。本書は、実践的な画面設計書のテンプレート(フォーマット)とその記述例を豊富に提示しています。 画面レイアウト図だけでなく、「画面項目定義書」「画面遷移図」「CRUD図」といった関連ドキュメントとの連携方法まで解説されており、明日からでもあなたのチームの設計プロセスに導入することが可能です。この「型」を知っているだけで、あなたの設計書の説得力と網羅性は、見違えるほど向上するでしょう。
この本を読むことで、あなたはこう変わる
『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』を読み込み、実践することで、あなたは以下のような変化を遂げるでしょう。
- 自信: 自分の設計に「なぜこうなっているのか」という明確な論理的根拠が生まれるため、自信を持って関係者に説明できるようになる。
- 信頼: あなたが作る設計書は、常に網羅的で分かりやすい。エンジニアやデザイナーから「この人の設計書なら信頼できる」と評価されるようになる。
- 効率: 設計段階で問題を潰し切るため、開発プロセス全体がスムーズに流れる。無駄な会議や手戻りがなくなり、本質的な作業に集中できる時間が増える。
- 成果: あなたが関わったサービスは、ユーザーにとって「直感的で使いやすい」ものになる。ビジネスの成果に直接貢献しているという、大きなやりがいを感じることができる。
これは、単なるスキルアップではありません。あなたの仕事のやり方そのものを変革する「投資」なのです。
第3部:『設計シリーズ:3』を血肉とし、さらに飛躍するための拡張ライブラリ(推薦書籍)
『設計シリーズ:3』は、画面設計の「骨格」と「作法」を教えてくれる、まさに土台となる一冊です。しかし、真のプロフェッショナルを目指すなら、その土台の上に、さらに専門的な知識を積み上げていく必要があります。
ここでは、『設計シリーズ:3』で得た知識をさらに深化させ、あなたの設計スキルを飛躍させるための「拡張ライブラリ」として、4つの領域から厳選した名著をご紹介します。
graph TD
subgraph "画面設計スキルの進化"
A["<b>『設計シリーズ:3』</b><br>骨格と作法 (WHAT & HOW)"]
subgraph "拡張ライブラリ (深化 & 拡張)"
B["<b>ノンデザイナーズ・デザインブック</b><br>UIデザインの原則 (WHY)"]
C["<b>誰のためのデザイン?</b><br>UX/人間中心設計 (USER)"]
D["<b>情報アーキテクチャ (シロクマ本)</b><br>情報の構造化 (STRUCTURE)"]
E["<b>マイクロコピーライティング</b><br>UXライティング (WORDS)"]
end
A -->|"論理的な配置の『なぜ』を理解"| B
A -->|"『ユーザー視点』の根源を理解"| C
A -->|"『画面間の繋がり』を設計"| D
A -->|"『コンポーネントに魂』を込める"| E
end
style A fill:#bde,stroke:#333,stroke-width:4px拡張ライブラリ1:UIデザインの「原則」を学ぶ — なぜそのUIは心地よいのか
『設計シリーズ:3』が「WHAT(何を)」と「HOW(どう書くか)」を教えてくれるなら、この領域の本は「WHY(なぜそうするのか)」という、より根源的な問いに答えてくれます。
【推薦書】『ノンデザイナーズ・デザインブック』(著:Robin Williams)
- どんな本か? デザインの4大原則である「近接」「整列」「反復」「コントラスト」を、これ以上ないほど分かりやすく解説した、全てのノンデザイナーにとっての入門書にして決定版。全世界で読み継がれる普遍的な名著です。
- なぜ『設計シリーズ:3』と相性が良いのか? 『設計シリーズ:3』で学ぶレイアウトの作法が、なぜ視覚的に分かりやすく、美しく見えるのか。その背後にある普遍的な「原則」を理解することができます。「なんとなく気持ちいい」を言語化し、再現性のあるスキルへと昇華させることができます。この本を読んだ後では、画面上のすべての要素の「距離」や「揃え」に、明確な意味を見出すことができるようになるでしょう。
- こんな人におすすめ:
- 自分の作る画面がごちゃごちゃして見える人
- デザインの基本的な「お作法」を知らないと感じる人
- デザイナーとの会話で、的確なフィードバックをしたいディレクターやエンジニア
拡張ライブラリ2:UXデザイン/人間中心設計の「視点」を学ぶ — ユーザーを神と崇める技術
優れたUIは、優れたUX(ユーザー体験)の一部でしかありません。ユーザーが本当に抱えている課題は何か?ユーザーはどのような文脈でサービスを利用するのか?その根本を理解せずして、真に「使える」画面は生まれません。
【推薦書】『誰のためのデザイン? — 認知科学者のデザイン原論』(著:Donald A. Norman)
- どんな本か? 「UX」という言葉が生まれる前から、その本質を説き続けてきた認知科学の大家、ドン・ノーマンによる不朽の名作。ドアの取っ手や蛇口といった日常にあふれる「悪いデザイン」を例に、なぜ人が道具の操作で混乱するのかを、アフォーダンスやシグニファイアといった概念を用いて解き明かします。
- なぜ『設計シリーズ:3』と相性が良いのか? 『設計シリーズ:3』が具体的な画面設計の手法を教えるのに対し、本書は「そもそも、人はどうやってモノを理解し、操作するのか」という、人間側の認知メカニズムを教えてくれます。この視点を持つことで、あなたが設計するボタンやフォームが、ユーザーのメンタルモデル(頭の中の思い込み)に合致しているかを判断できるようになります。「ユーザー視点に立つ」とはどういうことかを、骨の髄まで理解させてくれる一冊です。
- こんな人におすすめ:
- ユーザーテストで「使い方が分からない」と言われがちな人
- 機能は正しいはずなのに、なぜかユーザーに受け入れられないと感じる人
- より本質的なレベルで「使いやすさ」を追求したい全ての人
拡張ライブラリ3:情報アーキテクチャ(IA)の「構造」を学ぶ — 分かりやすさの骨格を作る
ユーザーが迷わない画面とは、情報が整理され、構造化されている画面です。どこに何の情報があるのかが一目で分かり、目的の場所にたどり着ける。その「分かりやすさの骨格」を設計するのが、情報アーキテクチャ(IA)の技術です。
【推薦書】『情報アーキテクチャ 第4版 ―見つけやすく理解しやすい情報設計』(著:Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango)
- どんな本か? Webサイトやアプリにおける情報設計のすべてを網羅した、通称「シロクマ本」。情報の「組織化」「ラベリング」「ナビゲーション」「検索」というIAの主要なシステムを、理論から実践まで体系的に解説しています。
- なぜ『設計シリーズ:3』と相性が良いのか? 『設計シリーズ:3』が個々の「画面」の設計に焦点を当てているのに対し、シロクマ本は「画面と画面のつながり」や「サイト全体の構造」をどう設計するかに焦点を当てます。グローバルナビゲーションはどうあるべきか?カテゴリー分けの最適な方法は?など、よりマクロな視点から「迷わせない」体験を設計する知識が得られます。個々の画面設計が「点」だとすれば、IAはそれらを結ぶ「線」と「面」の設計技術です。
- こんな人におすすめ:
- サイトマップや画面遷移図の作成に悩んでいる人
- ユーザーから「どこに何があるか分からない」と言われることが多い人
- 大規模で複雑な情報構造を持つサービスの設計に関わる人
拡張ライブラリ4:UXライティングの「言葉」を学ぶ — UIに魂を吹き込む魔法
画面を構成する最後の、しかし最も重要な要素は「言葉」です。ボタンのラベル、エラーメッセージ、説明文。これらのマイクロコピーが、ユーザーの行動を決定づけ、サービスの印象を左右します。
【推薦書】『マイクロコピーライティング』(著:山本琢磨)
- どんな本か? UI上の短い言葉(マイクロコピー)が、いかにユーザーの行動やコンバージョン率に影響を与えるかを、豊富な事例と共に解説した実践書。ボタンの文言を「登録する」から「無料で試してみる」に変えるだけで、どれほどのインパクトがあるかを具体的に示してくれます。
- なぜ『設計シリーズ:3』と相性が良いのか? 『設計シリーズ:3』で定義する「画面項目」の、具体的な「文言」をどう決めるかという問いに、完璧な答えを与えてくれます。設計書に記述するラベルやメッセージの一つ一つに、マーケティング的な視点とユーザー心理に基づいた戦略を込めることができるようになります。ロジカルに配置されたUIコンポーネントに、この本で学んだ「魂の言葉」を乗せることで、あなたの画面は初めて完成します。
- こんな人におすすめ:
- フォームの離脱率が高い、コンバージョン率が上がらないと悩んでいる人
- エラーメッセージが不親切で、ユーザーを怒らせていないか心配な人
- 言葉の力で、もっとユーザーを後押ししたいと考えている人
第4部:知識を「実践」に変える — 明日からあなたができること
さて、ここまでであなたは、優れた画面設計の重要性を理解し、そのための強力な武器となる書籍を知りました。しかし、最も重要なのは、この知識を「実践」に移し、あなたの血肉とすることです。
graph
subgraph "Step 1: 基礎固め"
A["『設計シリーズ:3』<br>を熟読・理解する"]
end
subgraph "Step 2: 技術習得"
B["Figma等のツールで<br>設計原則を具現化"]
end
subgraph "Step 3: 実践と展開"
C["担当画面で<br>『小さな成功』を創る"] --> D["成功体験を基に<br>チームを巻き込む"]
end
subgraph "Step 4: 継続的成長"
E["拡張ライブラリで<br>知識を深化・拡張"] --> F["設計文化を<br>組織に根付かせる"]
end
A --> B --> C
D --> E --> FStep 1: まずは『設計シリーズ:3』を熟読する
何よりも先に、『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』を手に入れ、最低3回は読んでください。
- 1回目: 全体を流し読みし、概要を掴む。
- 2回目: 実際に自分が関わっている、あるいは過去に関わったシステムの画面を思い浮かべながら、「この本の通りに設計したらどうなるか?」を考えながら読む。
- 3回目: 本書で紹介されているドキュメントフォーマットを参考に、簡単な画面で良いので、実際に自分で画面設計書を書いてみる。
Step 2: ツールを使いこなす
現代の画面設計は、Figma, Sketch, Adobe XD といったデザインツールと共に行われます。これらのツールは、単に絵を描くだけでなく、「コンポーネント」や「スタイル」といった概念を用いて、設計思想を具現化するのに非常に役立ちます。特にFigmaは、共同編集機能に優れ、チームでの設計作業に不可欠なツールとなっています。 『設計シリーズ:3』で学んだ設計原則を、これらのツールの機能を使って表現する訓練をしましょう。
Step 3: 小さく始めて、チームを巻き込む
いきなりプロジェクト全体の設計プロセスを変えるのは困難かもしれません。まずは、あなたが担当する一つの小さな画面から、本書のフォーマットを参考に設計書を作成してみましょう。 そして、その設計書を使ってエンジニアや関係者とコミュニケーションを取ってみてください。おそらく、以前よりも格段に議論がスムーズに進むことを実感できるはずです。その「成功体験」が、あなたのチームに新しい設計文化を根付かせる第一歩となります。
結論:あなたは「設計」で、未来を変えられる
私たちは今、あらゆるサービスがデジタル化され、ユーザーインターフェースを通して世界と繋がる時代に生きています。そんな時代において、「分かりやすく、使いやすい画面を設計するスキル」は、もはや一部の専門家だけのものではありません。それは、質の高いプロダクトを生み出し、ビジネスを成功に導き、そして何より、ユーザーの毎日を少しだけ豊かにするために、すべての開発関係者が身につけるべき「必須教養」です。
曖昧な指示と手戻りのループに、これ以上あなたの貴重な時間と情熱を浪費してはいけません。
今回ご紹介した『設計シリーズ:3 画面設計書 (画面レイアウト)』は、その混沌に終止符を打ち、あなたの仕事に「論理」と「自信」という光をもたらす、確かな一歩です。そして、そこから広がる拡張ライブラリの世界は、あなたを唯一無二のプロフェッショナルへと押し上げてくれるでしょう。
設計とは、未来を予測し、問題を未然に防ぎ、理想の状態を定義する行為です。 あなたの手で、ユーザーを迷わせない「道」を描いてください。 あなたの手で、開発チームを混乱させない「地図」を創ってください。
その力は、間違いなくあなたの中に眠っています。さあ、最初のページを開き、あなたのキャリアの「再設計」を始めましょう。
-

【設計シリーズ】システム開発でよく使う設計書 TOP20
システム開発の現場で必須となる設計書をTOP20ランキングでご紹介。開発の起点となる要件定義書から、品質保証のためのテスト仕様書、円滑な運用を支えるマニュアルまで。各ドキュメントの役割と重要性を簡潔に解説し、プロジェクト全体の流れを可視化します。エンジニアやPM必携の知識です。
続きを見る